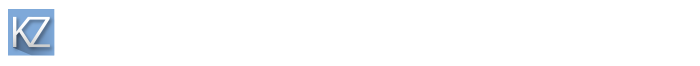大橋博理事長 × 榊原洋一先生 対談

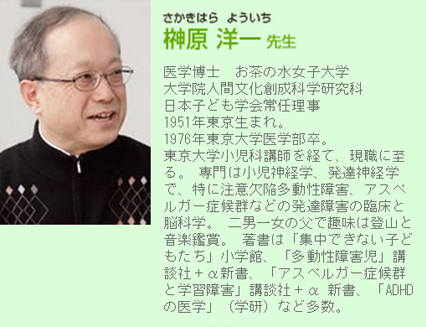
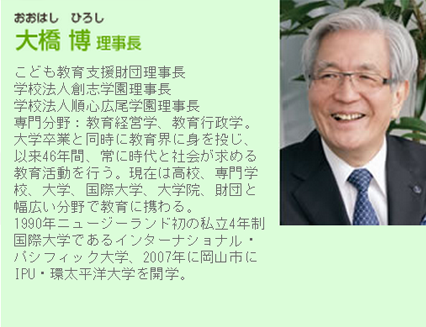
発達障害のあるお子さんもずっと付き合っていくと、特徴がわかってきて、
一般の先生方でも教えることができるんです。(榊原)
大橋 文部科学省は、先日、特別支援教育について本格的に取り組 む方針を打ち出しました。これは、そうしたサポートを必要とする児童、生徒が確実に増えていることの表れではないかと思いますが、先生はどうお考えですか。
榊原 以前、私はてんかんや脳性まひのお子さんを多く診ていたのですが、最近は落ち着きがなかったり、社会性が十分ではない、いわゆる発達障害と呼ばれるお子さんの割合が多くなっています。学会 でも、かつてはそういう研究発表は行われなかったのですが、昨年は 一番多かったですね。文部科学省は、「小1プロブレム」(入学したばかりの小学生が集団 行動に適応できない問題)などをきっかけに、そうした状況に気づいて調査を行い、2003年に最初の調査結果を発表しました。それによると、通常学級の生徒の6.3%が発達障害といわれるような行動の特 徴を持っているということです。何らかの支援が必要な子どもがこのようにたくさんいることが明らかになり、特別支援教育についての方針が出されたのだと思います。
大橋 ただ、具体的には誰がそうした子どもの面倒を見るのか、その生徒を取り巻く学校あるいは地域の意識はどうあるべきか、人材や施設の整備など、解決しなければならない課題は山のようにありますね。
榊原 そうですね。現場も地域も専門家も、すべてゼロからスタートということで、なかでも先生方は一番大変です。これからどうしようかということで、山積する問題と格闘しているのが現状だと思います。
大橋 今日はこの発達障害という問題について、親や学校がどう対 応していけばいいのか、先生にいろいろお話を伺っていきたいと思います。まず、親たちは発達障害に対しての意識をどれくらい持っているのでしょう。子どもに障害があっても「うちの子はほかの子と 比べて落ち着きがないな」くらいにしか思っていない場合もあるでしょうし、「ひょっとしたら、これは障害なのかもしれない」と思っても、それを認めたくないという気持ちも当然ありますよね。
榊原 少子化が進んで、今は子どもの数も、地域における子ども達のグループも減りましたから、初めて接する子どもが自分の子という親御さんも珍しくありません。そうすると、自分の子どもだけしか見ていないので、「子どもってこんなものか」と思い、比較する対象 がないんですね。そのため、親御さんたちは発達障害について知識はあっても、自分の子が果たしてそうなのか、なかなか判断できないということが実際に起きています。
大橋 そうすると、発達障害についての啓発活動を、学校や地域がもっと行っていかなければいけないということでしょうか。
榊原 主にマスコミや育児の本、あるいは教育現場でも啓発活動は行われていますが、まだ親御さんに十分浸透しているとは言えませ ん。その点、先生達の意識はかなり先行していますが、発達障害と思われるお子さんが自分のクラスにいると気づいても、そのことを親御さんが納得できないケースが非常に多くなっています。そうした先生と親御さんの橋渡し役としてスクールコーディネーターという役割が生まれたのですが、自分の子どもは発達障害の可能性がある、と学校に判断されることは親御さんにとっては非常に辛いことで、そこに齟齬が生じているのが現状だと思います。
発達障害は教育だけでなく日本の将来に関わる重要な問題
大橋 親の方も、なぜうちの子が発達障害になったのか、理由や原因が今ひとつはっきりわからない。だから納得できないし、そういう障害は治るのか、治らないのかという点についても、もうひとつはっきりしない。学校の先生としても、親からそうした質問をされ、「実は 治療法があるわけではなく、治っていくものではないですよ」なんてことは大変言いづらいですよね。そういうことを考えると、これを文部科学省だけの問題にしておいていいのか、社会全体の問題として見ていくべきではないかということもあります。
榊原 やはり一番大きな問題はマンパワーとお金なんですね。ただでさえ教育予算が増えない状況の中で、文部科学省も辛いところだと思います。先生方は学力の問題とか、子どものいじめとか非行の問題などで手いっぱいなところに、発達障害の子どもにもきちんと対応していけないということで、もうこれ以上、抱えきれないというような状況になっているんですね。校長先生などアドミニストレーション(学校の運営管理)に関わる方たちも、限られたリソース(裁量)の中で、何とか乗り越えなくちゃいけないと苦しんでいます。特に公立の学校はアドミニストレー ションの面で、あまり自由なリソースができないので、特別支援が必要な子どもに対して、積極的に取り組むことが難しい面があります。
大橋 こうした問題について、文部科学省と他の省庁との連携は行われているのでしょうか。
榊原 厚生労働省はどちらかというと医療的な面からこの問題を見 ていて、例えば専門家、保健センターや発達専門の医師などに対して啓発を行ったり、研究費を出しています。ただ、文部科学省以外の省庁の管轄と学校サイドとが必ずしもうまく合ってないという状況があると思いますね。
大橋 これは非常に大きな社会問題だと思います。ですから文部科学省、厚生労働省などと分けて考えず、もっと多方面から連携しないと、日本の国力を考える上で今後、大きな問題になってくるのではないかという危惧が非常にあります。
榊原 おっしゃる通りだと思います。例えば落ち着きがない、集中 できない、あるいは衝動的になってしまう注意欠如多動性障害(ADHD)という発達障害があります。これは、日本の子どもの中で5%ぐらいいると思われます。アメリカでは先行研究が行われていて、ADHDの子どもの約4割が非行に走るという調査結果も出ています。そういう子ども達が高校や大学を出ても就職できないマイナス面を考え、特殊な矯正教育を行う場合、年間で6000億円から7000億円の費用がかかるといった試算も出しています。まさに、理事長がおっしゃったようにこれからの日本を支える国力に関わる問題なんですね。教育や医学だけではなく、社会形成につながってくると言えます。当然、就労問題にも関わってきますし、実際に発達障害の人が労働災害に遭うケースも多いことから、労働などに関わる省庁が関わるべきなんですが、私が見る範囲では、まだ 日本ではそういう視点ではとらえられていないと思います。
専門家でなくても経験を積めば教えられる

大橋 この問題は、医学界も教育界も、もっと真剣にとらえないといけないと思います。ただ、まず親が子どもに障害があることを認めたがらないという問題がありますね。障害を認めた場合も、インクルーシブ教育(障害の有無などで分けず、さまざまな背景を持つ子どもが共に育つ教育体制)をしてほしい、あるいは特別な先生をつけてほしいなど、いろいろな希望が入り乱れている状態で、教育界自体も今すごく難しい状態になっています。
榊原 日本の教育界、特に公立の場合は運営管理する側のお金や人事に関する権限が決して大きくないので、思い切ったリフォームができません。インクルーシブ教育についても、理念としてはそういう方向に向かおうと言いながら、体制作りが十分できていないのが現状です。アメリカでは約15%の子どもが、いわゆる特別支援が必要とされています。私は昨年9月にインクルーシブ教育を行っているニューヨーク郊外の公立中学に行ってきたのですが、校長先生に「特別支 援を必要とする子どもが何人いるのか」と尋ねたところ、全校生徒700人のうち100人いるということでした。その中学校は地域でも有名な進学校なんですが、そういう学校でもインクルーシブ教育をしているんですね。このような実例を見ると、やればできるということがわかります。実際、日本でもクラーク記念国際高等学校などいくつかの学校では、インクルーシブ教育に近い形で、どんな子どもも一緒に育てていこうという流れが生まれています。それがモデルケースになって、「こうやればできるじゃないか」というような方向に行くことが重要かなと。私はそういう学校が、日本でもっとできるといいと思います。
大橋 今お話に出たクラーク記念国際高等学校も、最初は中退の子 が多かったのですが、やがて不登校やひきこもりなどいろいろな子どもが来るようになりました。明治の頃の教育は国民を優秀な軍人や勤労者など、決まったパターンに育て上げていけばよく、それからはみでる人間は、おかしいとさ れてきたわけです。でも、今はもうそれでは収まらず、子どもも多様化しています。今日のテーマとなっている発達障害も含め、本当にいろいろな子ども達がいるという前提でやっていかなければならないと思います。実際、発達障害の子ども達がクラスに占める割合は、とても増えていますね。
発達障害の問題は、多方面から連携しないと、日本の国力を考える上で今後、大きな問題になってくるのではないかという危惧が非常にあります。(大橋)
榊原 確実に増えています。もちろん、過去にも学力が遅れがちな子どもなどがいましたが、クラスのみんなで一緒に育っていこうという考えがあり、もっと柔軟性があったと思います。でも、少子化が進んで子どもに対する期待が大きくなった分、非常に1人1人に対する管理が細かくなり、そういう子どもがクラスの中で居づらくなっている。そういう兆候が起きているのではないかと思います。学力中心主義で、優秀な子どもを育てて世界の中でトップになるという方向に力が入りすぎて、今まではいろいろな子ども達を育てていくという視点が、少しなおざりにされていたように感じます。そういう意味で最近、クラーク記念国際高等学校のような学校がいくつかできていることは、やっとそういう視点が日本にも生まれて来たのではないかと思います。
大橋 しかし、学校の現場では、発達障害の子ども達に対処できる人材の不足が大きな問題になっています。特別支援教育の専門家的な先生をもっと増やさないといけないんじゃないでしょうか。
榊原 この間アメリカに行った時に、非常に面白い本と出会いました。教室のバイブルと呼ばれる、「プレリファーラル・インターベン ション・マニュアル」という分厚い本です。子どもに発達障害があるか、専門家に問い合わせる前にまずこういうことをやってみましょうというマニュアルなんです。学校でよく見られる200以上の問題行動に対し、それぞれ50ぐらいの解決法が書いてあるんですね。まず それをやってみて、だめだったら専門家に聞きましょうと。そこには、発達障害があると思われる子ども達も、まずは通常のクラスで受け入れようという精神が現れているんですね。私は感激して、この本を翻訳して日本で出版しようと思っています。日本では今、特別支援教室などができてくる中で、自信がない先生は、少しでも発達障害の傾向があるお子さんがいると、「特別支援学級に行ってください」と自分のクラスから外に出す傾向が生まれています。実際、この数年間で特別支援学級の生徒が5割ぐらい増えているとも聞いています。そういう先生はある意味、良心的で正直で、自分は経験がないから特別支援学級の先生の方がいいと考えるのかもしれませんが、私は、一般の先生方が自分達でそういう子ども達を教えることを学ぶ必要があると思ってます。やはり、最終的なカギになるのは一般の先生だと思うんですね。先生方がそういうお子さんに対応できるようにならないと、解決しないんです。
大橋 クラスの中で発達障害がある子も一般の生徒と学ばせ、いかに一般の生徒となじませるか。そういうことができる先生がむしろ必要じゃないかということですね。
榊原 専門家ももちろん必要ですが、どうしても専門家でなければと思うのは間違いで、発達障害のあるお子さんもずっと付き合っていくと、特徴がわかってきて、専門家でなくても教えることができるんですよ。かつての先生はそういうことをわかっていて、「どんな子どもであっても障害なんてない。自分達で見ていけば教えられる」といったことを言っておられた時期があったと思います。しかしだんだんと専門性を求められていく中で、自分が自信がないことについ ては専門家に託す、という方向になっているのだと思います。とは言え、専門家の先生もうまく配置されてないんですね。たとえば、私の知人の弟さんは新任の体育教師として赴任してすぐに特別支援学級を受け持ちました。しかし、その方は教師として通常の教育を受けているだけで、障害児教育を受けていないんです。最近、ノイローゼやうつ病を患う先生も増えているということですが、先生の能力に合った適正な配置が十分に行われてないのかなと。やや僣越ですが、そう感じますね。
発達障害の子どもを中心に親と学校がチームづくりを
大橋 もし自分の子どもが小学校の先生から、「お宅のお子さんは発達障害ですよ」と言われたときに、親はそれをどうとらえ、どうすればいいんでしょう。
榊原 その場合、どこに行けばいいのかといえば、もちろん「お医者さんに行って、診断書をもらっていらっしゃい」という話になるんですね。しかし、その時の親御さんの気持ちとしては、先生から突き離されたという感じになるんですよ。これはやはり好ましくないことです。またアメリカの例になりますが、アメリカではそういうお子さんがいると、必ずその学校地区と教育委員会が専門家の委員会を作り、個別指導計画(IEP)というものを作ります。そこには必ず先生と医師、心理カウンセラー、地元の代表者や弁護士など5~6人が参加し、そのお子さんについてどうすればいいか、親も意見が言える立場で参加するんですね。でも、そういうシステムが今の日本にはないんです。親御さんや先生方は発達障害のある子のために協力し合わなくてはいけないのに、発達障害があるかもしれないということが、むしろお互いに反目したり、敬遠することにつながってしまうんですね。障害のある子どもを中心にチームを結成し、一緒に考えることが極めて重要なのですが、今はそういう場がないんです。スクールカウンセラーが役立つ場合もあるんですが、課題もあっ て、個人情報の守秘が重要だっていうことで、情報がオープンにならないんですね。スクールカウンセラーとそのお子さんとの間だけで完結してしまい、そのお子さんについて、チームで対応するという発想がないんです。
大橋 カウンセリングの守秘義務は確かに大事だと思いますが、この問題の場合、それを言っているだけでは、解決する状況ではないと思います。
榊原 おっしゃる通りで、発達障害はスクールカウンセラー1人だけ、カウンセリングだけで解決できる問題ではないです。学校という集団、クラスの中での対応を考えていかなくてはなりませんから。私のところに来る親御さんにどうしたんですかと聞くと、「うちの子は障害があるかもしれないから、診てもらえと言われた」と、傷心で本当にがっかりして来られるんです。そして「私たちにはわからないんです」と。つまり障害があるかもしれないということだけを言われ、親御さんが心配して病院に来ているんです。学校と親御さんが、情報を共有できていないという問題は非常に大きいですね。
大橋 学校の中でも、そうした情報を知るのは校長など限られた一部の人達で、オープンにできないのかもしれませんね。しかし、教育界や医学界を含めて、日本でもこのような発達障害の子どもたちの教育や今後の生き方について、もっと全体的に考えるシステムを作る必要があるように思います。
榊原 親御さんは学校側から「この子は障害があるかもしれません」と言われると、そうかもしれないと思っていても、身構えてしまうんですね。それは、学校から出ていけと言われるのでは、という不安と恐怖感がとても大きいからです。その時に、先生方がそうではない、学校の中でこの子も一緒にやっ ていくんだ、それが大前提ですと言っていただくことが大事。そこが担保されると、親御さんは気持ちがすごく楽になります。その上 で、専門家の意見も取り入れていきましょうと言うと、親御さんも心を開いて専門家にかかれると思うんですね。
多様な子どもの受け入れが将来の日本の方向性を示す

大橋 たとえばクラーク記念国際高等学校で、子どもが中退をしてしまってどうしていいかわからないお母さんに「学校が面倒見ますから、任せてください」と言うと、とても元気になるんですね。実際に子どもが通い始めると、本当に安心されます。
榊原 ただ、残念ながらそういう学校は多くないですね。校長先生も十分権限があるわけではなく、校長先生が「どうぞいらっしゃい」と言っても、現場の先生方が「難しいです」と言われ、校長先生も辛い立場になるということがあります。私は、そういうことをきっちりできるような大きな権限を持ったアドミニストレーターのいる学校がいろいろな子どもの受け入れを進めていくことが、今後の日本の将来の方向を示してくれるんじゃないかなと思ってます。私はこれまで、何人ものお子さんにクラーク記念国際高等学校をお勧めしていて、この間も1人合格して、お母さんが報告にきてくれました。今まではクラスの中でいじめられたり、先生から苦情を言われていたのに、学校がこちら側に立ってくれたという感じが持てたと、とても喜んでおられました。
大橋 クラーク記念国際高等学校の先生は特に発達障害などの専門家ではないのですが、「また困ったことがあったら一緒に保護者会で考えましょう」と言われるだけでも、親御さんにとってはとても力になるようです。
榊原 それは素晴らしいことだと思います。専門家ではないとおっしゃいましたが、やはり学校を運営するトップの方が「どんな子どもも引き受けるんだ」という姿勢をしっかり持って、現場の先生たちを下支えしているから、先生方もリラックスして受け入れられるのですよ。往々にして成績や偏差値を上げろというプレッシャーの中で、先生も板挟みになっている可能性がありますが、それがない分、安定した対応ができるというのもあると思います。教職を選ぶ方は、やっぱり子どもが好きだし、教えたいという気持ちが強いと思うんですね。
大橋 その通りです。基本的には皆そうなんですよ。
榊原 しかし、それが十分にできない中で、発達障害の子どもに対応しなければいけない場合、悪循環に陥ってしまう面があるようですね。こうすればうまくいく、という例を示す意味で、私はクラーク記念国際高等学校など先進的な取り組みをしている学校に注目しています。
大橋 こども教育支援財団としては、クラーク記念国際高等学校と連携して、学習心理支援カウンセラーが問題を抱えた子ども達とどう対応すれば問題の拡大を防げるか、いいコミュニケーションを図りながら適度な距離を保つにはどうするか、といったことについて、かなり勉強してきました。今後、それらの実績を核にして、全国の先生達に研修を行うことも最近考えています。
榊原 それは素晴らしい考えだと思います。私たち医療関係者も、発達障害については、もっと教育界と一緒にいろいろな取り組みをしていく必要があるのではと思っています。たとえば医療の側からとらえた発達障害について学校の先生方に講義をしたり、一緒に勉 強することは非常に必要だと思います。
大橋 ぜひ機会があれば、今後の活動の一つとして力を入れたいと思っていますので、ご協力いただければと思っております。
榊原 ぜひ、協力させていただきます。
大橋 本日は榊原先生から日本の教育界あるいは医学界が抱えている問題について、大変貴重なお話をいろいろお聞かせいただきました。今日のお話を参考に、こども教育支援財団も今後、活動の方向を特別支援教育にも広げていきたいと考えています。今日はどうもありがとうございました。(了)