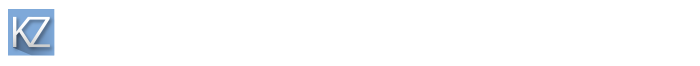表彰式・作品レポート
2025年度の受賞作品をこのページでご紹介します。作者のコメント・審査委員の講評も併せて掲載しています。
| ブロック | 東日本 | 西日本 | 海外 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学1~3年生の部 | 100点 | 40点 | 31点 | 171点 |
| 小学4~6年生の部 | 54点 | 42点 | 21点 | 117点 |
| 中学生の部 | 496点 | 334点 | 3点 | 833点 |
| 合計 | 650点 | 416点 | 55点 | 1121点 |
今年は国内からは1067点、海外は6の国から55点の作品が集まりました。
2025年11月9日に、明治記念館 蓬莱の間にて、表彰式を開催しました。第17回環境教育ポスターコンクール表彰式との同時開催です。会場には受賞作品が展示され、審査委員による講評も同時に掲載されました。


子ども作文コンクール表彰式では、受賞者に表彰状・副賞が授与されました。文部科学大臣賞の受賞者からは、受賞した作文を朗読していただきました。


受賞者による作文朗読の様子はこちらの動画でご覧いただけます。※文部科学大臣賞の朗読動画3本です。
- 【文部科学大臣賞】
- 静岡市立長田西小学校3年 髙田 昊太郎
- 【文部科学大臣賞】
- 愛知県立千種聾学校5年 長坂 蒼大
- 【文部科学大臣賞】
- 須磨学園中学校1年 西阪 実紘
式の最後に、審査委員長の内田信子様より、作品全体の講評をいただきました。
今の作文朗読、皆様感動しながらお聞きになったと思います。
小学校低学年の方、高学年、中学生、それぞれの特徴が良く表れた作文であったと感じられたのではないでしょうか。併せて1,121点応募してくださいました。その中から、私たちはとても素晴らしい作文、心に残る作文、先生に対する気持ちが我々の気持ちを揺さぶるような作品を審査しながら、選んでまいりました。
本日配布した受賞作品集には受賞作品23点が載せられております。学校の先生に限らず、家族や歴史上の人物、時には幼い子供に対しても自分の生き方を変えてくれた、考え方を変えてくれた、その先生へ敬意と尊敬の念を表している作文がとても多く見られました。
自分が何か大切なことを学んだ経験について具体的な交流、例えば先ほど朗読をした受賞者の看護師の方との体験、「涙の後には笑顔が来るよ!」この作文の中には6回もこのフレーズが繰り返されています。しかし、この繰り返し方が、最後の方ではこれから先、涙があっても笑顔になれるように努力していきたい。挑戦していきたい。というフレーズに変わっていくところが見事でした。
人生の師としての先生への敬意と感謝の念をなぜ抱いたのか、これが良く伝わる作文がこの作品集に掲載されております。小学校低学年では先生と思う人との交流を素直に表現する作文が多く見られました。中には筆圧が弱くて、少し読みにくい作文もありました。しかし、総じて原稿用紙に向かって自分の想いや感情を書き表すことに一生懸命取り組んでいる姿が窺われ、とても好感が持てました。小学校高学年では自分の人生に影響を与えてくれた先生との交流を通して感じたことや考えたことを丁寧に表現する作文が多くなりました。中学生では内省力が育ってくるのに裏付けられて、読み応えのある作文が多く、巧みな筆運びに引き込まれるようでした。自分の想いや考えを伝える作文は子どもの創造力や思考力を育てるとても良い機会となっています。
私はワープロで整然と並んでいる文字列よりも手書きで書かれた作文から書き手の考えや感情が良く伝わってくるように思いました。このコンクールが手書きの良さについて、省察する機会になってくれたら嬉しく思います。1,121点の作文から複数の審査員によって、特に優れているという作品が作品集の中に掲載されています。しかし、ここに掲載されていない作文の中にも心温まる作文が数多くあった。ほとんどの作文は受賞に値すると言っても過言ではないと思います。したがってこの作品集に掲載された23の作文はあくまでも1,121の作文の代表として挙げさせていただいているということを付け加えさせていただきたいと思います。本日授賞された皆様、誠におめでとうございました。
この受賞で終わる事なく、明日からも沢山の先生と出会って下さい。
そして素敵な文章を来年も送ってくれたら嬉しいなと思っています。
本日は誠におめでとうございます。


| 文部科学 大臣賞 |
小学1~3年生の部 | 静岡市立長田西小学校 3年 | 髙田 昊太郎 |
|---|---|---|---|
| 小学4~6年生の部 | 愛知県立千種聾学校 5年 | 長坂 蒼大 | |
| 中学生の部 | 須磨学園中学校 1年 | 西阪 実紘 |
| 理事長賞 | 小学1~3年生の部 | 福岡市立箱崎小学校 3年 | 渡邉 碧生 |
|---|---|---|---|
| 小学4~6年生の部 | 東京都立大塚ろう学校城東分教室 6年 | 中島 莉希 | |
| 中学生の部 | 宜野湾市立嘉数中学校 2年 | 名嘉眞 彩音 |
| 学研賞 | 小学1~3年生の部 | 宇都宮市立富士見小学校 3年 | 宮岐 諒大 |
|---|---|---|---|
| 小学4~6年生の部 | 松山市立道後小学校 4年 | 北地 勇輝 | |
| 中学生の部 | 須磨学園中学校 1年 | 新倉 美桜 |
| 審査員特別賞 | 小学1~3年生の部 | お茶の水女子大学附属小学校 1年 | 桝井 メアリ |
|---|---|---|---|
| 小学4~6年生の部 | 練馬区立春日小学校 4年 | 金井 花奈 | |
| 中学生の部 | 須磨学園中学校 1年 | 原田 和喜 |
| 優秀賞 | 小学1~3年生の部 | 笛吹市立一宮北小学校 2年 | 上原 士和 |
|---|---|---|---|
| 小学4~6年生の部 | 江東区立豊洲小学校 5年 | 小坂 玲菜 | |
| 中学生の部 | 横浜市立早渕中学校 3年 | 渡邉 文姫 |
| 入賞 | 小学1~3年生の部 | 愛媛大学教育学部附属小学校 2年 | 若狹 早 |
|---|---|---|---|
| 小学1~3年生の部 | 大阪府立高津小学校 2年 | 金城 梨沙 | |
| 小学4~6年生の部 | 町田市立町田第四小学校 4年 | 宮田 晴風 | |
| 小学4~6年生の部 | 会津坂下町立坂下東小学校 6年 | 石田 倭士 | |
| 中学生の部 | 広尾学園小石川中学校 1年 | 加藤 那々佳 | |
| 中学生の部 | 和歌山県立田辺中学校 1年 | 羽竹 紗希 |
| 海外賞 | 小学生の部 | 小学生の部 | 牛山 陽寿朗 |
|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 中学生の部 | ヘーゼル ナイア |
■ 文部科学大臣賞
 小学1~3年生の部
小学1~3年生の部
何でも調べるお母さん
静岡市立長田西小学校 三年 髙田 昊太郎
ぼくのお母さんはべん強が大すきだ。わからないことがあるとすぐに知りたいらしい。いつも本を読んでいるし、よく
「行ってみよう。」
「やってみよう。」
と言って何でも自分でたしかめる。
三年生さいしょのさんかん会。たんにんの先生が、
「パイナップルの中で一番あまいのはどこだろう。」
と聞いてきた。ぼくは、全ぜんわからなかった。お母さんを見たら、にやっとわらっていた。こん談会が終わって帰ってきたお母さんは、パイナップルをかかえていた。
「お母さん、どこがあまいか気になったから買ってきちゃった。」
さすがお母さん。さっそくいっしょに食べてみた。ぼくが、
「パイナップルって下にいけばいくほどあまい。なんでだろう。」
と言うと、お母さんはくだものの図かんを読み始めた。ぼくははじめてパイナップルの実のでき方を知った。そして、
「地面に近い方があまくなるのかな。」
とつぶやいた。すると、お母さんが、
「どうだろう。気になるね。」
と言った。ぼくは図かんを読みながら、
「ほかのくだ物も食べる部分によってあまさがちがうのか食べてみよう。」
とつたえた。ぼく、お母さんみたい。お母さんはやさしくわらって答えた。
「今どいっしょにスーパーへ行こうか。」
ぼくは毎日、本を読む。お母さんに負けないくらいの物知りになりたいから。そして、お母さんがまだ知らないことをたくさん教えてあげるんだ。
【髙田さんの作品に対する講評】
パイナップルのエピソードを例に挙げて、読書好きで勉強好きのお母さんの好奇心と行動力がいつの間にか昊太郎さんの学びの姿勢になっていることが生き生きと伝わってきます。疑問に思ったことや知りたいと思ったことは、本を読むだけでなく実際に自分の体験を通して確かめていく、とっても素敵なお母さんですね。
 小学4~6年生の部
小学4~6年生の部
笑顔と勇気をくれる人
愛知県立千種聾学校 五年 長坂 蒼大
「涙の後には笑顔が来るよ!」
この言葉は僕を勇気付けてくれる、とても大切な人から教えてもらった言葉だ。
僕には先天性難聴という障害があり、生まれつき耳が聞こえにくい。三年前に人工内耳の手術で神戸市にある病院に入院することになった。不安で泣いてばかりいる僕に、
「すぐに手術は終わるから心配ないよ」
と母は励ましてくれたが、「手術」という言葉を聞くたびに心がしずみ、逃げ出したくなった。入院当日も怖くて玄関にしがみついている僕を、困り顔の母が抱えて神戸の病院まで連れて行った。そこで出会った一人の看護師さんこそ、泣いてばかりの僕に「笑顔」と「勇気」をくれた忘れられない大切な人だ。
「涙の後には笑顔が来るよ!」
と言いながらその人は僕の頭をなで、優しくほほえんだ。その手の温かさは今でも忘れられない。でも、当時の僕には言葉の意味がよく分からず、ずっと考えていた。看護師さんは、続けてこう教えてくれた。
「手術が怖くて泣く子はたくさんいるけど次に会うときには、たくさん聞こえるようになったよって笑顔で教えてくれるんだよ。」
本当にそうなのかなと思ったけれど、看護師さんの手の温かさと笑顔を思い出すと、手術への不安が和らいでいくのが分かった。手術の日の朝、震えながら看護師さんに言われた言葉を心の中で何度も唱えた。涙の後には笑顔が来る。うれしいことが必ず来る。するとなぜだか勇気がわき、前よりも少しだけ強い自分がいることに気がついた。僕はベッドに迎えに来た看護師さんの顔を見て、涙目で大きくうなずいた。
手術が終わり、気がつくと病室のベッドに寝ていた。人工内耳の手術後はマッピングという音合わせが必要で、調整が終わるまでに数か月かかる。その間は聞こえるようになったのか分からないので、当時の僕も本当に不安だった。看護師さんは巡回で僕のベッドに来るたびに、優しい笑顔で励ましてくれた。いつの間にか僕は不安になるたびに、涙の後には笑顔が来るから大丈夫と自分に言い聞かせるようになった。退院の日に見せてくれた看護師さんの最高の笑顔が忘れられない。
あれから三年が過ぎ、僕の耳は以前よりよく聞こえるようになり、手術を受けてよかったと心から思う。あの看護師さんにまた会えたら、飛び切りの笑顔を見せたい。本当のことを言うと、今でも僕は怖がりで、初めて何かに挑戦するときは手が震え、涙があふれてくる。でも涙の後には笑顔が来ると心の中で唱えると看護師さんの笑顔が浮かび、勇気がわいてくる。この先も耳の聞こえにくさから壁にぶつかることがたくさんあるだろう。でも僕はもう逃げない。涙の後にはきっと最高の笑顔を浮かべている僕がいるから。
【長坂さんの作品に対する講評】
めったに経験することはない「手術」。誰だって恐いし不安になるでしょう。そんな不安な心や言動を自分の紹介とともに丁寧に書くことができています。だからこそ看護師さんの手の温かさや笑顔とともに「涙の後には笑顔が来るよー。」という言葉に重みがあるのですね。この体験がその場限りでなく以降の生き方の支えになっていることに説得力を持たせています。
 中学生の部
中学生の部
「なぜ?」を考える心
須磨学園中学校 一年 西阪 実紘
なぜ平行四辺形の面積は底辺×高さで求まるの?と先生は聞いた。
僕がその先生に会ったのは小学校五年生の時。初めての授業で算数とは論理的思考力をきたえる学問だと言っていた。僕はそれを聞いて不思議な先生だと思ったことを覚えている。
今でも覚えているのは図形の面積の求め方の授業。先生は僕達に問題を解け、ではなくなぜその公式で求まるの?と聞いた。だれも答えられなかった。公式を知っている人はいても、なぜなのかはだれも説明できなかった。先生は僕達に紙を渡し、その一時間、考えてみるように言った。授業の最後、自分で考えた理由をノートに書かせた。初日は三角形、次は台形、またその次は、というように、その単元が終わるまで僕達は考え続けた。当時の僕は算数がきらいだったが、「なぜ?」に自分の力で挑むのはとても楽しいと感じた。
それからも円の面積の求め方、分数の割り算など、先生はいつも公式を教えるのではなく、僕達が自分の頭で考える授業をしていた。その「なぜ?」について考える授業が僕は好きだった。
先生はいつも知っていることと、できることはちがう、というのが口癖で、知っているだけではなく、できるようになりなさいとよく言っていた。図形の面積を求める授業でも公式ぐらい知っていると言ったのに対して、なぜその公式なのか説明できますか?と言っていて、僕はそこで、人に言われるだけではだめで、自分の力で考えることが大切だと学んだ。
先生がいつも、何よりも大切にしていたのが論理的思考力だ。先生はいつも論理的に物事を考えなさいと言っていた。何々だからどうという風にいつも説明したり、させていて、自分のなんとなくの考えを見直すきっかけにもなった。
そして、僕は今日も楽しいと思いながら生きている。先生のおかげで「なぜ?」を考えながら生きている。そんな風に生き方を変えてくれた先生は、全てにおいて僕の先生だ。
【西阪さんの作品に対する講評】
五年生のときの算数の先生は、「公式を覚えるのではなく『なぜ』を考えなくてはいけない」と教えてくれた。このとき以来、いつも「なぜ?」を考えるようになってから、自分の力で挑むのは楽しいと感じるようになった。さらに、自分の考えを見直し、別の考えがあることにも気づくようにもなったという。論理的思考を育てることに注力する先生に出会えた歓びと感謝の念がひしひしと伝わってきます。
■ 理事長賞
 小学1~3年生の部
小学1~3年生の部
そばにいるよ
福岡市立箱崎小学校 三年 渡邉 碧生
「足の青あざは何?どこでけがしたと?」またお母さんに聞かれた。ぼくはいつも通り「え!分からん。いつの間にかできとった。」ととぼける。正直に言えない理由があるんだ。
ぼくは学校が終わるとおじいちゃんの家へ帰り、一しょに遊ぶのが日か。おじいちゃんはいつでも手かげんなし。手先がき用で、おもちゃ作りだってしんけん。わりばし鉄ぽうでしゃてきをしたり、だんボール空気ほうで線こうのけむりをとばしたり。理科の先生だったから、その知しきをフル活用させていろんな遊びを教えてくれる、さい強でさい高の先生なんだ。二人で本気で遊べば青あざができる事だってある。む中だからいたみなんかどうって事ない。こんなに楽しい時間をじゃまされるのはごめんだから、これからもお母さんには言わないつもりだ。
ぼくは一年生の時、学校のプール開きでおぼれてしまった。たまたま見ていたお母さんがとびこんで助けてくれたけど、次の日から学校に行けなくなった。うまくせつ明できないけど学校がこわくなったんだ。おじいちゃんは何も言わず、いつも通り本気で遊んでくれた。学校のぼくの朝顔の水やりにも毎日行ってくれた。そのうち、おじいちゃんと一しょなら少しずつ学校に行けるようになった。今ぼくは、元気に学校へ通っている。
六月、おじいちゃんがたおれた。おばあちゃんからの電話に、お母さんはひくい声で
「うん。うん。きゅうきゅう車よんで。」
とだけ言い、すぐ出ていった。後でお母さんが、心ぞうの病気でしゅう中ちりょう室にいるけど元気に話せると教えてくれた。よかった。今日一しょにはく物館に行くやくそくをしていたけど行けなくて、おじいちゃんがあやまっていたって。なみだがぼろぼろ出た。
「き間げん定公開なのに。」と思ってすぐはずかしくなった。おじいちゃんは病院でがんばっているのに、ぼくは自分の事だけを考えてしまったから。しばらくなみだが止まらなかった。心にはいろんな気持ちがあって、なみだにちがいがある事もおじいちゃんが教えてくれた。
じいじ、早く元気になって帰って来て。これからもいろいろな事を教えて。ぼくが手かげんするからまた一しょに遊ぼう。今度はぼくがじいじのそばにいるよ。
【渡邉さんの作品に対する講評】
碧生さん、とてもあたたかい作文でした。学校がおわったらまっすぐおじいちゃんの家へ行くようすが目にうかびました。理科の先生だったおじいちゃんが、おもちゃを作ってくれるのはとてもたのしそうですね。おじいちゃんといっしょにすごすじかんをたいせつにしている気もちがよくつたわりました。じいじが早くよくなるといいですね。これからもそのやさしい心を大切にしてください。
 小学4~6年生の部
小学4~6年生の部
聾の先生との出会い
東京都立大塚ろう学校城東分教室 六年 中島 莉希
私の担任は聾の先生だ。先生が話すときの手話はメリハリがあって、読み取りやすくて字がとんでもなくきれいな先生だ。さらに算数のノートをきれいにまとめることが上手な先生でもある。おかげで、私は算数が得意で毎回テストで百点を取ることができ、両親や妹にいつも自慢している。
そんな先生が担任になったのは、五年生の時だ。それまでは先生と全く話したこともなく、どんな先生なのか詳しく知らなかった。また、スパルタ教師らしいといううわさもあった。
五年生の四月、担任が発表された時、予想外の結果に私はぼうぜんと先生の顔を眺めていた。
当時の私は人見知りだった。それに、私はそれまで聞こえる先生が担任だったため、手話と声を使ってコミュニケーションを取っていた。しかし、聾の先生が担任になるのは初めてだ。私もお母さんも手話が分かるかなと不安だった。
しかし、私の不安はすぐにどこかへ飛んでいった。予想とは裏腹に、話してみると話しやすく、また、優しい先生だった。スパルタだといううわさはガセネタだったのだろうかと思うくらいだった。そんな先生が担任になってから、すぐに仲良くなった。人見知りだったはずなのに、最近は周囲の友達にも積極的に話しかけるようになった。しかも、手話が下手だった私は、手話のスピードが速い友達とスムーズにコミュニケーションを取れるようになり、手話でおしゃべりすることが楽しくなった。
また、あんなに作文が嫌いだった私は、先生のおかげであっという間に作文を書くことが好きになっていった。先生は苦手なものを「好き」に変える魔法使いと言っても過言ではない。
さらに意外なことに、先生は演技が上手だった。授業中も私たちがわかりやすいように演技を入れながら説明してくれる。また、文化祭の練習の時になると、先生はいつも演技の指導に熱心だった。先生が作る台本はとても面白くて、ついつい夢中になってしまうほどだ。
これまでの私は、作文も算数も演技も全て苦手だった。しかし、たった一年で変わった。それはもう先生のおかげだとしか言えない。先生は苦手を好きに変える魔法使いだ。私には、もう苦手なものは無くなったと言ってもいいかもしれない。だけど、さすがの先生でもお化け屋敷が大の苦手な私を克服させることは難しいかもしれない。
【中島さんの作品に対する講評】
担任の聾の先生が、スパルタとのうわさは「ガセネタ」で、本当はとても優しく話しやすい先生だったのですね。先生と仲良しになってから、クラスの友達ともおしゃべりするのが楽しくなったし、苦手だった作文も好きになっていったのです。まさに「先生は苦手を『好き』に変える魔法使い」なのですね!こう気づくまでの心の動きがていねいに表現されていて、とても読み応えのある作文でした。
 中学生の部
中学生の部
見つけられた私
宜野湾市立嘉数中学校 二年 名嘉眞 彩音
先生、私を見つけてくれてありがとう。
私は小学四年生の頃から話すことは楽しくても発表することが大の苦手になっていました。手を挙げることすらできなく、間違いを恐れていたはずです。そんな私をそばで見てきた先生は言いました。
「発表することが苦手なのなら、作文も自分の想いを伝える手段だよ。」
と、発表とはまた別の選択肢を提示してくれました。
その第一歩として勧められたのは道徳です。授業で行う道徳の教材を家庭学習としても取り組んでみたらどうだろうと。読んでみての感想やこれからの生き方など、自分なりに考えをまとめていきました。教材を通して、様々な見方や立場を知ってもらうことが狙いだったのだと今ならわかることができます。
そしてもう一つ勧められたのは、新聞を読むことでした。読解力の向上や現在の社会情勢、日本の歩んだ歴史など情報をたくさんインプットすることができる便利なものです。新聞だからこそ関心のないものでも、目に情報が入ることで視野が広くなると教えてくれました。今朝読んだ新聞の内容を話題とした会話もでき、知識が豊富になったことでより会話が弾んだこともありました。
先生と過ごす空間は私にとって心地いいものでした。いつも親身になって寄り添ってくれるからこそ、気軽に相談することができます。先生に作文で認められたい思いが、今でも私の力になっています。
四年生の三学期、私は作文のコンクールで入賞することができました。先生の手助けもあり、自分の伝えたいことをまとめられたと思います。あの時の達成感は忘れることができません。しかし、同学年には最高位を受賞した子がいたのです。一番得意だと思えたものを簡単に壊されたように感じて、心から祝うことができませんでした。
「あの子は学年にあった素直な表現だから今回は選ばれたけど、あなたは表現が豊かだからいつか選ばれる日は来るよ。」
と先生は励ましてくれました。二年間、応募を続けた結果、三回目で私は最高位を受賞できたのです。悩んだ分だけ、努力は伝わる気がします。先生は何度も応募して諦めなかったことが大切なことだったのだとほめてくれました。先生と一緒につかみ取った思い出深い作文です。
私は作文が好きです。先生と出会えたから今の私とも出会うことができました。見守りつつも的確なアドバイスをくれる先生の支えがあってこその私でした。私はもう中学二年生です。先生との出会いから四年の月日が流れました。先生と会う機会もなくなっています。それでも、私の心には先生との日々があります。私はこれからも作文と向き合い続けます。納得のいくものがつくれたあの日のように。
【名嘉眞さんの作品に対する講評】
彩音さん、とても心を動かされる作文でした。発表が苦手な自分をそのままにせず、先生といっしょに新しい表現の力を見つけたことがすばらしいです。先生に励まされながらあきらめずに三回目の挑戦で最高の賞をつかんだ努力が、文章から強く伝わってきました。これからも作文を通して自分を表す力をのばし、自信をもって成長していってください。
■ 学研賞
 小学1~3年生の部
小学1~3年生の部
小さなセンセイ
宇都宮市立富士見小学校 三年 宮岐 諒大
先生とは何か。ぼくが「先生」という漢字を初めて習ったのは一年生の時だ。「先に生きると書いて、センセイと読みます。」と教えてもらった。先に生きるということはぼくよりも年上、ということだとその時に考えたのを覚えている。でも、今は少しちがう。
ぼくは今も放課後はようち園に行っている。学童があるからだ。小学生の仲間と遊ぶのも楽しいけれど最近は「小さなセンセイ」にいろいろと教わることがある。三さいのアオ君はぼくに多くのことを教えてくれる。
アオ君はとてもかわいい。一緒に石を集めたり、どろで楽しく遊んだりすることもある。笑顔で遊んでいても別の子が来るとちょっといやそうな顔をする。石をアオ君の小さなぷっくりとした手においてあげると、それをぎゅっとにぎって、笑顔でぼくを見る。その後に別の子に石をあげると泣きそうな顔になる。ぼくに見ていて欲しいのかな、とそんな時にぼくは感じる。きっと、ぼくのお母さんもそのように感じながら小さかったころのぼくといてくれたのだろうと思う。
ある時、ぼくが帰るのに急いで荷物を取りに行ったことがある。ふり返るとアオ君は目をうるうるさせてぼくを遠くから見ていた。だから、ぼくはもどって、アオ君のやわらかい手をやさしく持って、ゆっくりとゆっくりと二人で歩いた。急いでいたけれど、アオ君に合わせて歩いた。きっと、ぼくのお父さんもそうやって小さかったころのぼくと歩いてくれたのだと感じた。
ぼくは赤ちゃんの時のことはあまり覚えていない。でも、アオ君といると家族のみんなやようち園の先生たちがどのようにして、そしてどのような気持ちで成長を見守ってくれていたかが少しわかる。アオ君は教えてくれる。アオ君はぼくの「小さなセンセイ」だ。
【宮岐さんの作品に対する講評】
三歳のアオくんが「先生」? そのわけは、「赤ちゃんのときのことは覚えていないけれど、アオくんと遊んでいると家族のみんなやようち園の先生たちが、どのようにアオくんの成長を見守っているかを教えてくれるとタネ明かししてくれました。諒大くんのアオくんへのやさしさに感動しました。
 小学4~6年生の部
小学4~6年生の部
いろいろな顔をもつぼくの先生
松山市立道後小学校 四年 北地 勇輝
「勇輝君、持ってきたぞ。」
軽トラックに大量の野菜をつんで、ぼくの家にやって来たその人は、近所に住んでいる西村さんだ。ぼくは一年生の時から夏野菜を家庭菜園で上手に育てる研究を続けている。肥えた広い畑で野菜を育てる環境がどの人にも平等にあるわけではない。そこでぼくは、プランターの種類や土の量、肥料を変え比較し、限られた場所でみんながより簡単に野菜作りができる方法を探っている。このことを知っている西村さんは、自家農園で収かくした大根、白菜、ネギ、じゃがいも、玉ねぎなど季節を感じることのできる野菜を届けてくれる。そしていつも、苗を植える時期、土の作り方、肥料をまくタイミングなど野菜作りのコツを細やかに伝授してくれるのだ。今年も西村さんのアドバイスをもとにプランターで甘いミニトマト作りに挑戦中だ。今、庭は青々と勢いのあるミニトマトの苗でうめつくされている。
ぼくは、西村さんを野菜作りのプロだと思っている。スーパーで売っているものと変わらないりっぱな野菜を作っているのに西村さんはそれに満足することなく、気こうや土の状態など、いつも本や資料を読んで勉強をしている。これこそがプロなのだといつも思っている。
野菜作り名人の他にも西村さんには別の顔がある。有害鳥じゅう駆除の資格を持っているのだ。祖母のみかん園地では、イノシシによる被害がたびたび起こる。一生けん命作ったみかんを食いあらしたり、木をたおされたりするのだ。電気ショックでわなにかかったイノシシを駆除してくれる西村さん。いつも農家の人たちから感しゃされている。電気ショックであっという間に死んでしまうイノシシの姿を見て、ぼくはおどろいて声も出せずにいた。すると西村さんは
「勇輝君、農家さんがとても困っている時には、どうしても駆除しなければならない。でも、そのあと感しゃをしておいしく食べたらいい。」と、どんな料理にすればいいか伝えて、さばいたイノシシ肉を置いていく。「いのち」をうばう駆除だけれど、「いのち」を大切にあつかうことを教えてくれる。
さらに西村さんは、ぼくが病気になれば心配してお菓子を持ってきてくれたり、進級祝いまで用意してくれる。今年八十才になる西村さんは、ぼくにとって野菜作りの師しょうであり、生きていくことのむずかしさや大切さを教えてくれる人だ。そして、いつも気にかけてくれるおじいちゃんのような存在だ。様々な顔を持つ西村さんは、ぼくにとって困った時に一番に相談したい大切な先生だ。もうすぐ研究中のミニトマトが赤く実る。研究成果をほう告する日が楽しみで仕方がない。
【北地さんの作品に対する講評】
勇輝さんにとって困ったときに一番相談したい大切な先生である西村さんは八十歳になる近所のおじいちゃん。野菜づくりの師匠で、生きていくことの難しさや「いのち」の大切さを教えてくれる西村さんから、動物、植物、人間、生きものすべてに対する愛を教わり、人としての生き方を教わっていることが適確な言葉で率直につづられています。
 中学生の部
中学生の部
ケケ
須磨学園中学校 一年 新倉 美桜
私の祖父母は、幸せなことに、皆元気に過ごしている。その中に、一際パワフルな人がいる。「ケケ」と呼んでいる母の母だ。なぜ、孫の皆から「ケケ」と呼ばれているのかは後にして、ケケは実際、小学校の先生だったが、私にとっても祖母というより、ちょっとした意味で「先生!」と呼びたくなる人である。
まず何といっても、「パワフルインフルエンサー先生」と呼びたい。先生は今年七十五歳だが、家でじっとしているイメージが全くない。一人で海外旅行に行くし、桜が咲いたら、九州から青森まで桜前線を追いかけて国内旅行をし、きれいな桜の写真を送ってくれる。万博が開かれたら、「足が棒。」と言いながら、元気に「今日で万博四回目よ。」と連絡が来る。インスタグラムを悠々と使いこなし、旅行やイベントでの美しい風景写真の投稿は千八百回を超え、二千人以上のフォロワーの中からメッセージをくれた人には律儀にお返事を書く。驚くのは、外国の人からのメッセージにも、その人の国の言葉で短い一文だけれど返事をしている。インスタグラムのストーリーズには、いつもピッタリな音楽をつけ、投稿を見ると一緒に旅行に行ったような楽しい気分になる。本当に七十五歳なのかと思うくらい明るく楽しい祖母だ。私は家では静かなつもりだが、中学に入りクラスメイトからは、すごく陽気な性格だと言われるようになった。どこかで、「パワフルインフルエンサー先生」の影響を受けて、明るく楽しく生きたいという血が騒ぎはじめたのかもしれない。
もう一つは、ケケは私の「お料理の先生」でもある。ケケの家に遊びに行く度に、何かお料理の作り方を教えてくれる。一番古い思い出は、幼稚園の時に一緒にしたコロッケ作りだ。ケケのコロッケは、なぜかいつもピンポン玉のようにまん丸だ。幼稚園の砂場での泥団子作りの感覚でコロッケを丸めるのが楽しかった。自分で作ったものは、魔法にかかったように全部食べられる。ケケはいつも、料理は作る人を笑顔にして、食べる人を元気にするものと教えてくれる。
私にとって「パワフルインフルエンサー先生」でもあり、「お料理の先生」でもあるケケは、なぜケケと呼ばれるのか。ケケは、「ケセラセラ(なるようになる)」のケイコさんの二つの「ケ」という頭文字をつなげて「ケケ」と孫の私達には呼んでほしいと母に頼んだと聞いた。どんなにつらいことがあっても、明るく楽しく元気よく生きていけば、なるようになるものだと信じている。元旦にケケからもらうお年玉袋には、毎年、「みんな明るく楽しく元気よく」と書かれている。このように、いつも行動で示して色々なことを教えてくれるケケは、私の人生に、ワクワクする刺激を与えてくれる大好きな先生だ。
【新倉さんの作品に対する講評】
身近に生き方のお手本になる「先生」がいるなんて素晴らしい事ですね。「ケケ」は、新倉さんの75才の祖母。「パワフルインフルエンサー」と呼びたくなる活動的で何にでも挑戦するエネルギッシュで魅力的な人物です。そんな「ケケ」が具体的で生き生きと描かれているのが優れています。また、祖母について単に紹介するだけでなく、孫として自分が何を受け継いでいるか自覚しているのが良く分かります。
■ 審査員特別賞
 小学1~3年生の部
小学1~3年生の部
私の先生はトンボ
お茶の水女子大学附属小学校 一年 桝井 メアリ
六月、学校のプールでヤゴとりをしました。あみを水に入れるとおもくなってたいへんだったけど、五ひきのヤゴをつかまえて、家にもってかえりました。でも、その日のうちに二ひきがともぐいされて、とてもかなしかったです。それでお父さんと赤虫をかいに行ってのこったヤゴにあげることにしました。
二しゅう間ぐらいして、一ぴきがせ中からうかしかけて、水の中でおぼれてひっくりかえっていました。見たとき、私はなきました。木のえだがたおれたからか、三十五どのあつさでつかれてしまったのかもしれません。どうして水の中にいたのにおぼれたのか、ふしぎでした。
つぎの日、べつのヤゴがフタにのぼり、トンボのかたちで出てくると思ったら、せ中がわれて白い体がひっくりかえりながら出てきて、私はドキドキしてねる時間もわすれてむ中になって見ていました。ヤゴより大きくなったトンボにびっくりしました。そのトンボはとぼうとしてフタにぶつかり、おちておぼれそうになったところをお父さんがたすけてくれました。もう一ぴきのヤゴはそれを見ていたのか、トンボになった時、はねをパタパタするだけでした。
朝、フタをあけてあげると、元気にとびたちました。でもおぼれたもう一ぴきはとべませんでした。私は「こうやってとぶんだよ。」とうでをパタパタさせておうえんしました。トンボもまねしてパタパタ。でも、その日はとべませんでした。
つぎの日、私が出かけようとげんかんの前に来たとき、私をまっていたかのように目の前をトンボがすうっととんでいきました。まるで私に「ありがとう。とべるようになったよ。」と言っているみたいでした。私は「とべてよかったね。バイバイ。またあおうね。」と言いました。
このトンボは、私にいのちのことや、あきらめないでがんばることの大せつさを教えてくれた、私の先生です。こんどは、どんな先生に会えるかな。きっと私をまっている気がしてたのしみです。
【桝井さんの作品に対する講評】
メアリさんは、ヤゴがうかしてトンボになってとびだしていくまでをていねいにかんさつして、きちんときろくしています。トンボは「いのちの大せつさ」や「あきらめないでがんばることの大せつさ」をおしえてくれた「先生」なのですね。
 小学4~6年生の部
小学4~6年生の部
「大きらい!から大好き!」へ
練馬区立春日小学校 四年 金井 花奈
四月、三年二組の黒板に千川原先生が書いた自こしょうかいにわたしはふるえ上がった。名前の頭文字を使った自こしょうかいで、
と書かれていたのだ。地球一なんておそろしいが、きっとこれは先生の冗談だろうと思っていた。しかし、授業が始まり、先生が本当に地球一こわいことがわかったのだ。
三年二組では、毎日漢字ドリルの宿題が出た。千川原先生は、とめはねはらい、書き順、細かいところまでてっ底的にチェックする。特にしんにょうは、永遠に丸がもらえないのでは、というくらい毎日直された。直しがこわくて、私は全力でえん筆を持って書くものだからペンだこができた。筆順チェックもきびしい。漢字テストで、「様」という字の筆順を間ちがえたら、先生はわたしが漢字を書いているところを見ていたわけではないのに、筆順ミスに気づいたのだ。まさに、地球一こわい漢字テスト・漢字ドリルの先生だ。
三年二組は、重たいタブレットを毎日持ってくるルールだ。家が遠いわたしは、タブレッ卜の重さで、かたにあざができた。学校にタブレットを置いておけるほかのクラスがうらやましかった。雨の日の中休みはタイピング練習をしなくてはならないし、ローマ字にも千川原先生はきびしかった。
そんな地球一こわい三年二組での生活を続けるうちに、わたしに変化があらわれた。漢字を細かいところまでていねいに書くようになり、字がきれいだといわれるようになった。ノートもきれいになった。地球一こわい、と思っていた千川原先生は、実は地球一注意深くわたしの文字を見ていてくれたのだ。そのおかげでわたしは習字や文字を書く場面で活やくできるようになった。漢字もとく意になり、四年生になってからも、漢字テストはいつも百点だ!
もう一つ、クラス替えがおきてわかったことがある。三年二組出身の子は、みんなタイピングが早く、総合学習の授業が楽に受けられるのだ。きびしい先生の指どうのおかげで、わたしたちはとく意なことがふえたのだ。
千川原先生は、他にもわたしを注意深く見て、必ずよいところを見つけてほめてくれた。読書好きなわたしに、「金井さんの語い力は読書のたまものですね!」と言ってくれた。先生は、私がよく読書をしていることに気づき、それがわたしの長所になっていることを教えてくれた。
先生は、三年生の最後の日、「前途洋々」という言葉を送ってくれた。一年間、地球一こわい先生は、わたしたちの未来が前途洋々になるよう、地球一細かく、愛をこめて見守ってくれていたのだ。こわくて仕方なかった先生は今、わたしの大好きな、尊敬できる先生だ。
【金井さんの作品に対する講評】
「地球一こわい、と思っていた千川原先生は、実は地球一注意深くわたしの文字を見ていてくれたのだ」このことに花奈さんが気づいたとき、大きらいな先生から大好きな尊敬できる先生に変わりました。子どもたちの未来を見すえて愛をこめて見守ってくれていた千川原先生に対する花奈さんの感謝の気持ちが伝わってくる秀逸な文章です。
 中学生の部
中学生の部
僕の料理の先生
須磨学園中学校 一年 原田 和喜
僕の料理の先生は母と父だ。僕は小さい頃から食べることが大好きな子供だった。お気に入りのトマトを切りたいと思い、誕生日に母からもらったプラスチック製の包丁で切ろうとしたところ、切れ味が悪く、かえって危ないと考えた母は、大人と同じ包丁を使うように言い、包丁の使い方を教えてくれるようになった。我が家はIHヒーターだったこともあり保育園を卒園するころには肉野菜炒めを一人で作れるようになっていた。
我が家で魚をさばくのは父の仕事だ。僕は父から「押し包丁」と「引き包丁」を教えてもらった。このような環境で、僕は当たり前のように包丁を持ち、料理をするようになった。
僕にとって料理とは時間を忘れ、熱中することができる大切なものだ。最初は心配して僕のことを見守ってくれた母と父に「ありがとう」と言いたい。
小学校二年生の時に母が近所にある和食屋に連れて行ってくれたことがある。そこではカウンターの目の前で料理を作ってくれるため、料理好きの僕にとっては見ていてとてもわくわくするような場所だ。大将が巧みに玉子焼き器を操り出汁巻き玉子を作る姿は本当に格好よく見えた。それをきっかけに僕は家で出汁巻き玉子を作るようになった。また、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令されていた際には、テレビで見たレシピを参考に、チャーハンやリンゴのピザ、チョコブラウニーなどを作るのが唯一の楽しみになっていた。
僕の母と父は、当たり前のように料理をするという習慣を僕に身につけさせてくれた。母と父はその他にも色々なことを実体験させようとさまざまな場所へ連れていってくれた。母と父の教えは色々なことに挑戦して自分の力でできることを増やしなさいということだと思う。僕はこれからも色々な料理を作っていきたいのと、新しいことにも挑戦していきたい。
【原田さんの作品に対する講評】
幼少期のエピソードからコロナ禍でのエピソードまで、料理が得意になっていった様子が詳しく書かれています。そして、和喜さんが当たり前のように料理をする習慣を身につけることができたのは、ご両親の教えのお陰であることが明快で説得力のある文章で綴られています。その教えは、料理だけにとどまらず新しいことに挑戦していこうという意欲につながっている点も素晴らしいですね。
■ 優秀賞
 小学1~3年生の部
小学1~3年生の部
ボブ先生とぼく
笛吹市立一宮北小学校 二年 上原 士和
コンコンコンとせきをしながら、いつもぼくをみてくれていた先生。今年の四月からは、もう先生のしんさつは、ありません。
はじめて先生に出会ったのは、ワクチンをうけにいった時でした。ボサッとしたボブヘアがかわいいめがねをかけたボブ先生。ぼくが大すきな小にかのおいしゃさんです。ぐあいがわるい時は、いつも先生にみてもらいました。
先生のすきなところは、ぼくがおこっても、ふざけても、いじわるを言っても、ニコニコしているところです。そして、ぼくの気もちをどんな時も見て、きいてくれます。先生は、ぼくがとってもおしゃべりなことを知っています。だから、しゃべらなくなると、ぼくのたいちょうがわるいことにすぐ気づくと言っていました。
ある時からボブ先生は、はなにチューブをつけて、さんそボンベをよこにおいて、しんさつをしていました。先生になぜかきくと
「もう、さんそなしじゃダメなのよ。」
と言いました。せきをよくしていたりゆうが、よくわかりました。自分の体がひどい中、ぼくたちのことをみてくれていたのです。
ぼくは、先生が、おいしゃさんて大へんなしごとなのよとおしえてくれたことを思い出しました。人生をかけて、さいごまで、おいしゃさんでありたかったんだと思います。でも今は、自分の体を大じにしてください。かんじゃさんより自分とむきあってください。
ぼくは、大きくなったら、おいしゃさんになることがゆめです。先生は、ぼくたちの心の声をきいてくれました。ぼくも先生のようになりたいです。気づいたことあります。ぼくにはじめて、家ぞくじゃない人からのあいをおしえてくれたのは、ボブ先生です。先生がくれたバトンは、ぼくがうけとります。
【上原さんの作品に対する講評】
士和さん、とても心のこもった作文でした。ボブ先生のやさしさと、びょう気でもがんばっているようすがしっかりつたわってきました。先生に「ありがとう」といえるきもちもすばらしいです。自分もいしゃになりたいというゆめをもっているのがとてもりっぱです。これからも人を思うやさしい心を大切にしていってください。
 小学4~6年生の部
小学4~6年生の部
私を変えた夢
江東区立豊洲小学校 五年 小坂 玲菜
私は、極度の引っ込み思案だった。そんな私を変えてくれたのが、四年生のときの担任の先生だった。私は最初、自分にこんなにも大きな夢ができるなんて思ってもみなかった。その夢こそ「学校の先生」である。
その夢ができたきっかけは、担任の先生の工夫した授業の教え方や、一人ひとりに対するサポートの仕方だった。例えば、その先生がとくいとする体育では、ジャンプの練習にマリオのキノコを取り入れてイメージしやすくしたり、普段その練習に使わないような道具を使ったりしていた。国語や総合では、様々なグラフや図、チャートを教えてくれたり、班で自分の考えを説明する機会を増やしてくれたりした。そのおかげで、一つひとつの授業の時間が、とても充実していたように思えた。
また、その当時、私の友達にも学校に来られない子や、来ても教室に行けない子がいた。そんな子たちをサポートしてくれていたのも、その先生だった。席を入口の近くにして入りやすくしたり、教室に来てくれたら、精一杯の喜びを表したり。すると、その子たちが学校や教室に来る回数がだんだんと増えていった。
そして、引っ込み思案な私にも気をつかってくれた。先生は、私がバレエを好きだと知ると、
「バレエ教えて!」
と声をかけてくれた。さらに、私を先生としたバレエ教室の生徒としてがんばって練習し、私を楽しませてくれた。おかげで私は、教えることが楽しいと知ったし、みんなが集まってきて、クラスが明るくなった。そして、今まで話したことのなかった子たちとも関われたのだ。私を引っ込み思案でおとなしい子と決めつけないで、私の可能性や活躍できる場所を引き出してくれた先生に感謝している。
先生に勇気をもらった私は、五年生になった今、学級委員に立候補して学校の代表としてクラスをまとめる役割を担っている。そして今でも会ったら必ずかけよって、あいさつをするようにしている。
先生と出会ったことで、勉強を教えることだけでなく、クラスのために、一人ひとりと向き合うということなども学校の先生の大切な使命なんだと気がついた。私はその先生の情熱と対応力に心を打たれ、自分を変えることができた。だから同じように、誰かに夢を与えられるような学校の先生を目指すことに決めた。まだその夢と思いは先生に秘密にしているけれど。いつか感謝の思いを伝えられたらいいなと思っている。その感謝の思いは、なぜだか担任をしてもらっていたときよりも強くなっている。ありがとう。先生。私に大きな夢と希望を与えてくれて。
【小坂さんの作品に対する講評】
玲菜さん、とてもすてきな作文でした。先生の楽しい授業や、こまっている友だちを助けたお話から、先生のあたたかい心がよく伝わりました。あなたが前向きになって、バレエもがんばれるようになったのがすばらしいです。これからも夢を大切に、大きくはばたいてください。
 中学生の部
中学生の部
墨の呼吸
横浜市立早渕中学校 三年 渡邉 文姫
硯の上で墨をする音が、私の新しい朝の始まりを告げる。岡谷先生との出会いは小学校一年生の春、書道教室の扉を開けた瞬間から続く墨の香りと共になる。先生は楷書の基本点画を教える際、必ず「筆先で息をしなさい」と言う。最初は意味がわからなかった。
「永字八法のここにね、生き物の呼吸が宿っているのよ」先生の手元を見ると、確かに横画を書く時にふっと肩の力が抜ける瞬間があった。硯に映る窓の光がゆらゆき、先生の銀髪が金粉を纏ったように輝く。 八十歳を超える今も、毎朝寺院で写経を欠かさないという。
転機は中一の夏。全国書道コンクールで特選を逃した夜、教室に忘れた題字用紙を取りにいくと、先生が私の半紙を広げて観察していた。「この跳ねに悲しみが滲んでいるわ。でもね・・・」突然硯に指先を浸し、滲んだ部分を蝶の形に描き足した。「失敗を飛翔に変えるのが書の妙味よ」
今年の正月、先生が脳梗塞で倒れた。右手が震えるのに、リハビリの合間に左手で般若心経を書いていた。「筆は心臓と繋がっているの。止まったら終わりよ。」
先月、初めて先生の代わりに寺の写経を任された。写経用紙に先生の呼吸法で筆を運ぶと、墨の粒が光の中を泳ぎ始めた。最後の文字を書き終えた時、ふと気付いた。滲んだ部分が先生の蝶のように羽ばたいていた。
今でも硯を磨りながら思う。先生が教えてくれたのは書の技術ではなく、生きる筆の運び方だったのだと。一滴の墨が千年の記憶を運ぶように先生の呼吸は私の中で永遠に続いていく。
【渡邉さんの作品に対する講評】
書道の先生との交流を通して、文姫さんは「先生が教えてくれたのは、書の技術ではなく、生きる筆の運び方だった」と悟っています。「一滴の墨が千年の記憶を運ぶように先生の呼吸は私の中で永遠に続いていく」との結びまで、ことば選びと文章表現の巧みさが読む者の心をわしづかみします。珠玉のエッセイに出会えたという、静かな慶びにひたっています。
■ 入賞
 小学1~3年生の部
小学1~3年生の部
わざありの先生
愛媛大学教育学部附属小学校 二年 若狹 早
じこしょうかいは、とってもだいじ。それはなかよくなるための、さいしょの一歩。たくさんの人に見られると、ぼくはちょっときんちょうしてしまう。でも、今は元気にお名前とすきなものが言えるようになった。どうしてかと言うと、二年星組たんにんのとよた先生が「わざあり」で教えてくれたから。
二年生になって二日目、じこしょうかいの時間がやって来た。とよた先生は、
「新しいクラスでのじこしょうかいは、一年に一回です。」
と言った。ぼくはドキッとした。ちゃんとできるかな。うまく言えなかったらどうしよう。とよた先生はつづけて、
「だから先生は一年に一回しか、自分の名前を言いません。きのう言ったので、もう名前をわすれてしまいました。」
「えーー!」
「そんなのうそだーーー!」
ぼくもみんなも、ケラケラわらった。さっきまでのきんちょうも、ふっとんだ。
「わすれてしまったので・・・・・先生の名前は、イカです。」
「それは先生がすきなものでしょ!」
みんなで大もり上がり。そうか、じこしょうかいはうまく言おうとしなくていいのか。みんなに自分のことを知ってもらえたらいいのか。とよた先生のおかげで、ぼくはじこしょうかいで一歩ふみ出すのが楽しみになった。
休み時間、とよた先生はいっしょにドッジボールをしてくれる。ボールを回しながらなげるとスピードが出るけれど、とよた先生は
「そーれ、ぐるぐるぐるー!」
ボールじゃなくて、体の方をぐるぐる回してしまった。へろへろのボールをなげて、みんな大わらい。とよた先生のボールのなげ方も「わざあり」なのかな。
【若狹さんの作品に対する講評】
「わざ」って何でしょうね。若狹さんは、自分にとっての「わざ」を担任の先生の言動から発見していきます。苦手だった自己紹介でも先生の「うまく言おうとしなくてもよい」姿から自分でも出来ると気づきます。ドッジボールでもみんなを大笑いさせる投げ方をするのも「わざ」だと思うのです。自分の気づきを「わざあり」として簡潔に書いています。読み手に一緒に考えてもらう表現力が優れています。
いじわる先生
大阪市立高津小学校 二年 金城 梨沙
わたしのバイオリンの先生はとてもきびしい先生です。一生けんめいれんしゅうした曲をひいても、すこしまちがえただけですぐに止められます。先生は、いじわるだといつも思います。でも、バイオリンが大すきなのでがんばるしかありません。
つぎのはっぴょう会の曲は、わたしにはむずかしい曲にきまりました。先生は、「君ならできる。」と言いました。やっぱりいじわる先生だと思いました。まい日がんばってれんしゅうをしているのに、むずかしくて、できなくて、くやしくて、なみだが出る日もありました。先生は、「作曲しゃがどんな思いで曲をかいたのか、イメージしてごらん。」と言います。わたしは、「そんなのわからないよ。」とまたいじわる先生だと思いました。でも、おかあさんがいっしょに作曲しゃのことをしらべてくれました。すると、曲にあったイメージがわいてくるようになりました。イメージがわくと、むずしかったところが少しずつひけるようになってきて、くやしくてないていたのに、うれしくてなきそうになりました。
はっぴょう会は、すごくきんちょうしたけれど、上手にひくことができました。先生は、「うん」とうなずいてニッコリはく手をしてくれました。とてもほこらしい気もちになりました。今は先生のことばがとてもあたたかくかんじます。できないことも、あきらめずにやればできるようになることがわかりました。
そのご、わたしは、かけ算がわからないことがありました。でも、バイオリンのけいけんを思い出し、あきらめませんでした。なわとびも一りん車も、このけいけんのおかげで、あきらめずにできるようになりました。先生のおかげでわたしはこれからも何にでもちょうせんできそうです。いじわる先生は、わたしの一ばんさい高な先生です。
【金城さんの作品に対する講評】
梨沙さん、とてもすてきな作文でした。むずかしいバイオリンのきょくにちょうせんして、がんばった気もちがよくつたわってきました。先生がきびしいのは、あなたの力をしんじているからなのですね。さいごに「さいこうの先生」と思えるのがとてもすばらしいです。これからも音をたのしみながら、どんどん上手になってください。
 小学4~6年生の部
小学4~6年生の部
大好き、西久保先生
町田市立町田第四小学校 四年 宮田 晴風
金曜日、私は黒服で学校に行く。書写の授業があるから。授業始めのあいさつで、いつも西久保先生は
「良いあいさつですね。」
と、隣のクラスまで聞こえる大きな声でほめてくれる。なんだか、みんな気持ちいい。西久保先生は小さなおばあちゃん先生。前は隣の学校の校長先生だった。私たち二七人全員を、孫のように思ってくれているみたい。
授業の最初は、その日の大切なことをみんなで確認する。先生は【止め・はらい・ここは長い】など注意するところを、何回も言ってくれる。聞きのがしてもまた言ってくれるから、良い。そしてお友達の書いた、雲という字を
「これはもう、お手本ですね」
と大きな声でほめていた。お友達がほめられているのを聞くのも、いい気持ち。私が書いた麦という字は、
「きれいな字。優秀賞」
と、言ってくれた。はらいやバランスが難しくて、一生けん命書いたので、認めてもらえて嬉しかった。上手くいかなかったら、一緒に書いてくれたり、なぞり書きしてから本番を書いても良いルールにしてくれた。優しい。清書用の半紙も、一人五枚と決まっていても失敗したら
「次の紙、取っていいよ」
と新しい半紙をくれる。わざとでなくても紙が汚れてしまうことがあるので、助かる。
授業中、分からないことを質問したら、
「質問してくれてありがとう。いい質問。これでみんなも分かるね」
と言う。「質問」と「答え」「ほめる」が一セットになっているみたい。西久保先生には特別質問しやすい。
それに、先生が話している時に、しゃべっている人たちがいても、
「こっち見てね。」
と言うだけで怒らないし、大きな声にして説明を続けてくれる。私は連帯責任で怒られるのは仕方ないと分かっていても、嫌な気持ちになる。個別で誰かが怒られたとしても、先生の話が途切れるから、やっぱり嫌。全然怒らない西久保先生が好き。なんで怒らないか先生に聞いてみたら、
「先生は子供が大好きなの。怒っていいことはないし、そのうち聞いてくれるようになると思う。みんなのこと、信じているの。」
と、笑顔で答えてくれた。優しい先生はたくさんいるけれど、とびきり優しい。そして、最近は西久保先生が話している時は、みんなちゃんと話を聞けるようになってきた。予言が当たった。
一週間に一回、一時間しか先生の授業はないけれど、大好き。前から書写は好きだけど、今は先生のおかげでもっと楽しくて好きになった。やっぱり西久保先生は私にとって、特別な先生です。
【宮田さんの作品に対する講評】
書写の授業での西久保先生のほめ言葉、しゃべっている人を怒らない理由、みんなの変化を晴風さんの気持ちも添えながら丁寧に描いています。だから、子どもたちのことをほめて、ほめて、認めて、信じて、とびきり優しい西久保先生の子どもたちに対する愛情の深さが伝わってきて、読んでいるととっても温かな気持ちになります。
全ての原点はここから
会津坂下町立坂下東小学校 六年 石田 倭士
ぼくの小学校生活はソフトボールで幕を開け、ソフトボールで幕を閉じる。ソフトボールと監督に出会えたから今の僕がいる。
「倭士!試合はまだ終わってない!」試合中に悔し泣きするたびに何度この言葉を聞き、何回自分を奮い立たせただろうか。一つのボールに夢中になる自分を好きになれたのは、常に厳しい言葉と前向きな言葉で僕のやる気を繋いでくれた監督のおかげだろう。
身体が小さい僕は、飛距離が伸びないことに悩んだ時期がある。練習後の自主練もした。それでも思うような結果が出ず自信をなくしていた時、監督が僕に武器を作ってくれた。バントと盗塁だ。足の速さに自信があった僕は、練習着が切れるまでスライディングの練習をし、走り出すタイミングを学び、肩のいいキャッチャーからもセーフがとれるようになった。監督が喜ぶ姿もうれしかった。バントの基礎を細かく学び、チームの一点に貢献できる技術をつかめたのも大きな自信に繋がった。この時、僕はチームに必要なんだと思うことができた。
高学年になった時、「倭士はホームランバッターじゃない、チームが勝つ為にどんな形でも塁に出るのが倭士の仕事だ。」この「どんな形でも塁に出るのが倭士の仕事だ。」という言葉が六年になり、キャプテンになった僕に今強く響いている。監督と作り上げた武器はチームの勝利に繋がっていると思う。今のチームは決して強いチームではないけど、一人一人が自分の役割を果たした時、思いもしない結果に結びつくと僕は信じている。その瞬間の喜びを監督やみんなと感じる為に今も練習に励んでいる。
幼稚園から始めたソフトボールと監督との出会いが僕の原点だ。ソフトボールは声を出すことの大切さとチームプレーの面白さを、監督は僕に自信をもつこと、その自信をもつために必要な根性を育ててくれた。優しい指導者が増えてる中、監督の指導は厳しいと感じるメンバーもいると思う。そんな時は期待されていると受けとめ、監督と向き合って欲しい。必ず努力は結果に繋がるから。
監督の指導と言葉で、欠点は使い方で武器になること、ゼロから始めることで新しい知識と技術が一つ一つ自分のものになった時、大きな自信になることを教えてもらった。その成果を実感している僕は、これから先、新しいことに挑戦した時やどんな試練とぶつかっても必ず乗り切れると信じている。この六年間で僕の基盤に整った。
今言いたい、「監督、六年間ありがとうございました!教えてもらったこと、一生忘れません。」
【石田さんの作品に対する講評】
「監督に出会えたから今の僕がいる」ソフトボール監督は、倭士くんが結果が出ず自信をなくしていた時、弱点に気づかせそれを克服する練習法を教えてくれたのです。監督への尊敬の念と感謝の気持ちが読むものの心をうちます。リズミカルにたたみかける表現力がきわだつ素晴らしい作文です。
 中学生の部
中学生の部
祖父の心と私のココロ
広尾学園小石川中学校 一年 加藤 那々佳
四つん這いになって歩いていた私。目線の低い私を小さなかごに入れて、飛行機にしてくれた人。フワッと宙に浮いたときの喜び。あまりにも楽しくて何度もおねだりした私。それが祖父と私の最初の記憶である。
あのときから約十年。私は中学校へ進学し、祖父は仕事を辞めて家にいることが多くなった。そんな最近の楽しみは、祖父とおしゃべりをすることだ。祖父の話で最も印象に残ったものといえば何だろう。やはり、祖父が子供の頃の話なのであろう。
戦時中に生まれた祖父は、中学生のときに投資を始めたそうだ。その理由は何だと思うだろうか。私は、単純に利益を得るためなのではないかと思っていた。しかし答えは違ったのである。確かに利益を得るためではあるのだが、もっと奥が深かった。祖父はこう言ったのだ。
「母のため。」
当時、祖父の家は小さく、トイレすらなかったそうだ。そのため、祖父は母に楽になってほしいと思い、投資をして利益を得ることにしたそうだ。そして、周りで投資をしている人は誰一人いないにもかかわらず、毎日新聞を確認して投資をしていたそうだ。この話を聞いたとき、祖父の優しさと勇気にとても驚いた。そして、当時の祖父の優しさというものは今も祖父の中に残っているのではないか。
先日、祖父の家を訪ねたとき、祖父はサラダを作っていた。その様子を見ていたら、ふと皿の数が多いことに気がついた。疑問に思った私はそのことを祖父に尋ねると、祖父は、祖母と叔父の分を作っているのだと言っていたのである。しかも、祖母の分は少なめで叔父の分は多めになっていた。とても身近なことではあるが、相手一人一人のことを考えることができる祖父はやはり素敵な心の持ち主だと改めて気づいた瞬間だった。
さて、話が変わるが、この文章のタイトルを思い出してほしい。タイトルを見たとき、あなたはこんな疑問が浮かんだのではないか。
「なぜ『心』と『ココロ』なのか。」
これには理由がある。祖父は、八十年以上この地球という場所で生きてきた。だからこそ、たくさんの経験を積み重ねてきた人であって、生きるための術を知っている。一方で私は、まだ十三年間しか生きていないので、心の中では生きるという文字がバラバラになっている。そう考えたときに、心は漢字一文字であって、長年経験を積んできて熟したこころという感じであって、ココロはカタカナで、未熟でぎごちない感じである。だから私は、祖父の心に教えてもらい、自分のココロを成長させたいのだ。人生百年時代。ゆっくりじっくり、ココロを心にしたいと思う。
もうすぐ先生の誕生日。今度は私の番だ。ココロなりの考え方を先生に教えよう。
【加藤さんの作品に対する講評】
「祖父」から何を学んだのかを書こうとして、いろいろ考えました。そこでどんな素材を集めるか、これが作文を書く時の大事な力です。たくさんあるエピソードからどんなことを取り上げたら自分の書きたい「祖父」になるのか、これが大切です。加藤さんは、芯の通った人柄を浮かばせたいと効果的な例を挙げています。題名の「心」と「ココロ」の違いまで構成を工夫して書くことができました。
人生の先生
田辺中学校 一年 羽竹 紗希
理想の人生について考えた時、その回答は将来何の仕事がしたいかや、結婚したいとか、どうやって死にたいかを考えると思います。
私の考える「理想の人生」とは、「人に優しく生きる」ことです。つまり、どのように生きていくかです。私の考える「人に優しく」とは、一人一人の個性を認め、尊重して人と関わることだと思います。
私にはそのためのお手本と言える存在がいます。それは、「やなせたかし」さんの描く「アンパンマン」です。最近、「あんぱん」という朝ドラが始まりました。このドラマは、「アンパンマン」を創ったやなせたかしさんと、妻である暢さんの人生をつづった物語です。このドラマを家族と見ながら、自分の見ていた「アンパンマン」は、作者がこのような経験をしたからできた話なのかと感じることができました。「アンパンマン」は、作者の「飢えている人を助けることこそ正義」という信念のもと、第二次世界大戦後に苦しんでいる人々を思って創られた物語ですが、当時はアンパンマンの顔を食べさせているところなどが残酷だと言われ、批判されたそうです。それでもあきらめず創り続けたことで、今でも放送が続く愛される作品となりました。
私は「アンパンマン」というキャラクターの「誰にでも優しく平等なところ」を尊敬しています。そして、この部分は作者の想いを表している素敵な部分だと思います。「飢えている人を助けることこそ正義」という作者の信念の通り、「アンパンマン」という作品は戦後の人々の心の支えとなり、勇気と思いやりの大切さを教えてくれる特別な物語として広まり続けています。私は幼稚園の頃、毎朝「アンパンマン」を見ていました。今でも心に残る親しみある物語ですが、作者のこのような信念から創られていることは知りませんでした。作者は「正義とは何か」を考え続け、自分の正義を信念として形に残していてすごいなと思ったし、信念を何よりも大事にする考え方も1つの個性だと思いました。幼稚園、小学校の頃と比べ、今では関わる人も増えてきました。だから私は、その中で初めて会う人の考えや個性を認め、取り入れていきたいなと思いました。
今回紹介した、アンパンマンと、やなせたかしさんは、人が困っていることに気づける人、相手の個性を認めて尊重することができる人たちで、そんなところが私が人生の先生と考えた理由です。私は「将来何をしたいか」まだ悩んでいます。しかしどんな職業に就くとしても、困っている人がいたら気づいて助けられるようにしたいと思っています。
【羽竹さんの作品に対する講評】
紗希さん、とても心に残る作文でした。幼いころから見てきたアンパンマンを、大人の目で新しく考え直しているところがすばらしいです。やなせたかしさんの思いを感じ取り、「やさしさ」や「信念」を自分の生き方につなげているのも、とても成長を感じます。その思いを大切に、どんな時も人を助けられる大人になってください。
■ 海外賞
海外日本人学校等からの応募作品に贈られる賞です。
 中学生の部
中学生の部
石の中に生きている先生
ドイツ ISR International School on the Rhine 小学六年 牛山 陽寿朗
僕は、この先生にあったこともなければ、話したこともない。なぜなら、この先生はもうこの世にいないからだ。この先生は石の中に生きている。
僕とこの先生の出会いは、僕がやっているポケモンGOというゲームの中だった。その石はポケストップというアイテムが出る場所の印に使われていた。僕は、その石のことが気になり、調べた。
その石は、つまずきの石(シュトルパーシュタイン)と呼ばれ、第二次世界大戦で犠牲になった人々を追悼するために、彫刻家のダンター・デムニッヒ氏が始めた。犠牲になった人の家の前の道路に石を埋め、ここに確かにこの犠牲者が住んでいたことを示している。
ナチス・ドイツの犠牲者のうち、ユダヤ人、障害者、政治的・宗教的被迫害者などは強制収容所に送られた。「一つの石には、一人の名前」という信念のもと、名前、生年月日、いつどこに強制連行されたか、その後その人はどうなったかがしんちゅうに刻まれている。
僕がゲームで見つけた石にはこう書かれている。『マリア・パッシャー、一九二九年生まれ、一九四三年にグレーフェンブルグに強制輸送された、一九四三年七月三一日に栄養失調が原因で死亡した。』
そう、僕の先生の正体は、ナチス・ドイツの犠牲者なのだ。
パッシャー先生は、ナチス・ドイツが行った独裁的かつ差別的行為を戦争が終わった今も忘れないように静かに僕たちに語りかけている。 パッシャー先生も、そのほかの先生もナチス・ドイツの犠牲になるまでは、ごく普通の市民として、この場所で普通の生活を送っていて、この家に住んでいたと知ったら心が痛くなった。
つまずきの石プロジェクトは、ドイツが過去にナチス・ドイツが行った行為を忘れないように、国が一部支援している。犠牲になった、六〇〇万人にも一人一人名前があり家族がいて、人生があった。このプロジェクトは、犠牲になった人々の権利を尊重していると思う。
今も世界中では戦争で毎日人が亡くなっている。しかし、その人々にも名前があり、家族と一緒に楽しい人生を送っていた。
僕は、インターナショナルスクールに通っていて、そこには、言語や文化が違う人がたくさんいる。通ってからわかったが、言語や文化は関係なくどの国の人とでも、クラスメイトとして、友達として、楽しく話したり、遊んだりできる。もちろん外国人と付き合うのは、難しいこともある。しかし、それはどこの国の人ではなく、人間としてうまく付き合えないだけなのだ。
僕の役割は、この作文を通して、つまずきの石を、そして、パッシャー先生の死を日本の人に伝えることなのだと感じている。パッシャー先生の死は、普通の市民の幸せな生活がナチス・ドイツにより一日で奪われることがあったということを僕たちに教えてくれた。
パッシャー先生は僕だけの先生ではなく、この出来事を学んだすべての人の先生なのだ。パッシャー先生はこの作文を通して皆さんの先生にもなったのだろうか。
【牛山さんの作品に対する講評】
インターナショナルスクールに通っていると、多言語・多文化に接することになります。牛山さんもそんな生活の中でさまざまな経験をしたり、日本の中では触れることのない知識を得ることもあるのですね。その一つが「つまずきの石」(シュトルバーシュタイン)です。牛山さんはゲームで知った知識をより深く学び今の世界にまで発想を広げ伝えたいと考えています。それを「先生」ととらえ、まとめました。
ことばを使わない授業
イギリス 北東イングランド補習授業校 中学三年 ヘーゼル ナイア
右足の外反母趾の手術を受けた。
四年間、週に三回通っていたダンスも、ちょうどシーズンに入ったクリケットもできなくなった。学校の行き帰り、友人との買い物や家族との散歩。元気に動き回っていた毎日が突然止まった。
お天気の良い日が増え、スマートフォンを見れば、友人たちが海や散歩に出かけている写真が載っていた。私も遊びに行きたい。太陽を浴びたい。そう思っても、術後はクラッチの使い方に慣れず、外出する気力もなくなって、家に閉じこもる日が多くなった。
手術をする前は、痛む足とお別れできると思っていた。しかし、現実はそう甘くはなかった。術後は強い痛みで思うように動けず、痛み止めが切れた時、すぐには薬が飲めないもどかしさに苦しんだ。一人でできていたことが家族の助けなしではできなくなり、「迷惑をかけているのかも」と申し訳ない気持ちにもなった。そして何より「大好きなダンスができなくなったらどうしよう」という不安や焦りがどんどん膨らんでいった。足の痛みが続くことで、心までしんどくなっていくのを感じていた。
一人では何もできない時間が増えた私は、「待つことの難しさ」と向き合うことになった。痛みに耐えることは本当につらく、薬に頼った。一日四回の痛み止めを六日間続けた。けれど、七日目。強い薬を三回だけで乗り越えることができた。足のむくみもほんの少し減り、足の指も、わずかに動かせるようになった。その時、心の波が少し穏やかになっていることに気づいた。小さな変化を感じた時、「ああ、時間が必要なんだ」と思えるようになった。
痛みも不安も、時間が少しずつ和らげてくれた。何もできない時間は、私を回復へと導く大切な時間だとわかった。「動けないことは決して無駄ではない」それが、時間が私に教えてくれたことだ。強い痛み止めを飲まなくても平気だった、傷口が少しずつふさがっていくのを感じた、青いアザが肌の色に近づいてきた・・・その一つ一つが「時間」という先生の静かな教えだった。
これから先、もし大きなケガをしたり、心が傷ついたりすることがあっても「時間が薬」だと信じて、笑顔で動き出せる日を待ってみようと思う。今もまだ足は完治していないけれど、「時間」という先生とともに、自分のペースで前を向いて歩いていきたい。
【ヘーゼル ナイアさんの作品に対する講評】
「先生」を自分を育み成長させてくれる存在ととらえると、その範囲は無限に広がります。ヘーゼルさんにとっては足の手術後の痛みや今後への不安の中にいる時間こそが「先生」だったのです。「時が解決する」とは、よく言われることですが、自分の経験を記述することで自覚していく姿が説得力を持たせています。一見、かけ離れたものに感じられるような書き出しから、これからの自分について内省的に描写することができました。